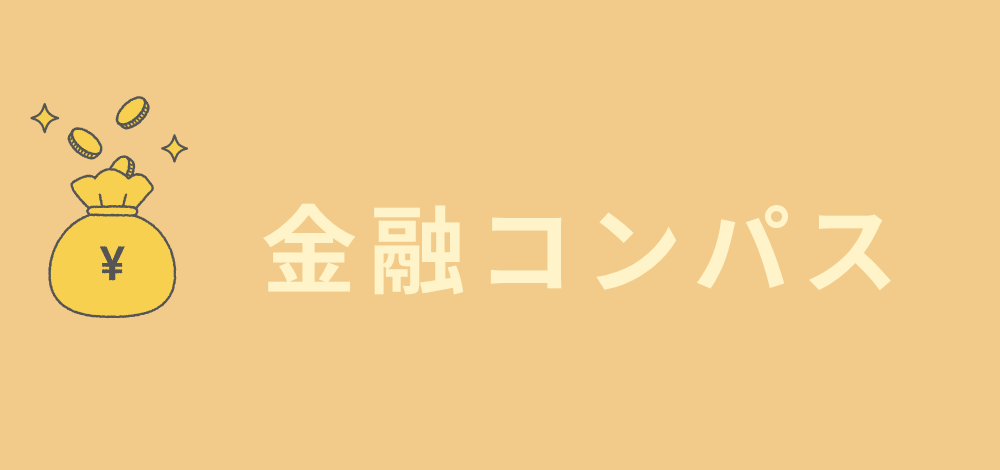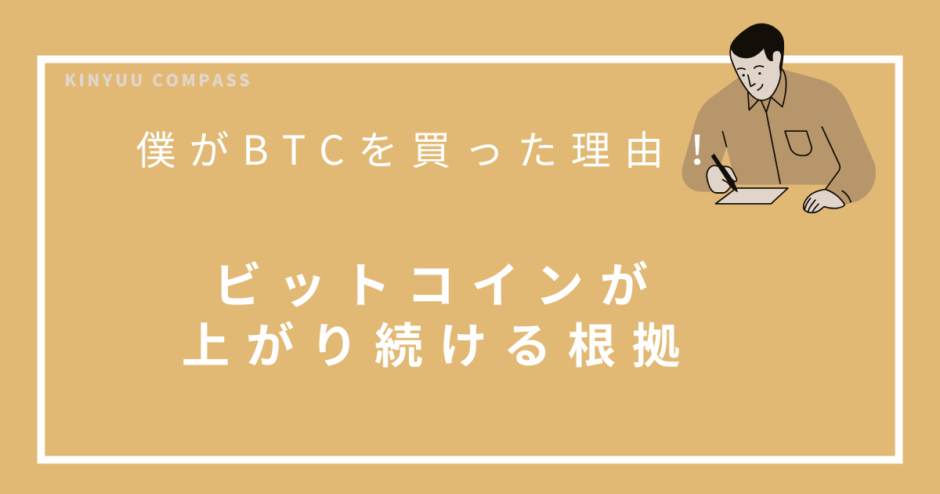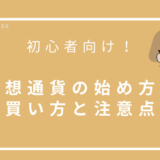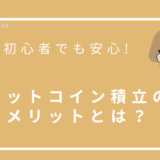この記事で解決できるお悩み

こんな悩みを解決できます!
投資歴7年、運用額6,000万円超の僕が解説します!
僕は、ビットコイン誕生の歴史や特質をしっかりと学んだ結果、確信を持って投資できるようになりました。
実際に、2025年2月から始めた仮想通貨投資では、資産額が10ヶ月で300万円以上増えています。
本記事では、ビットコインがなぜ上がり続けるのかをその特質から分析し、メリットや将来性についても深掘りしていきます。
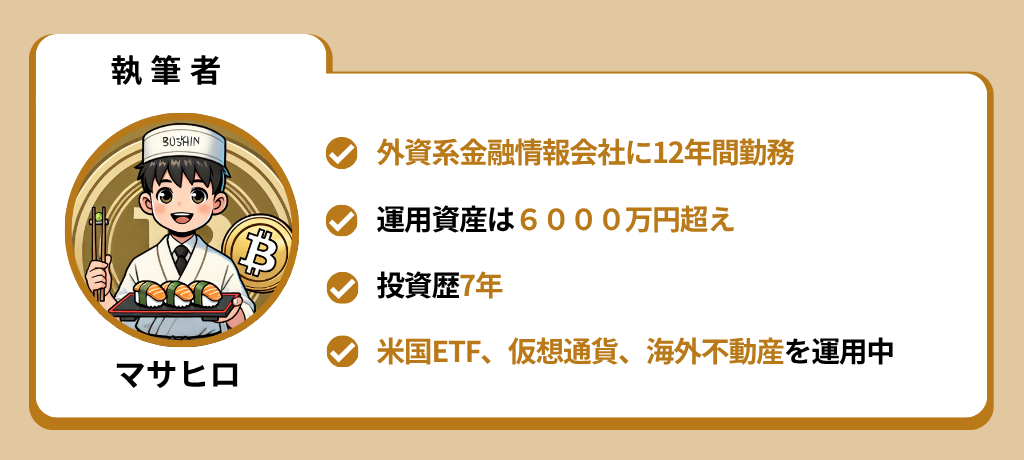
仮想通貨の元祖「ビットコイン」とは

ビットコインは仮想通貨の1つですが、そもそも仮想通貨って何なのでしょうか?
仮想通貨とは、簡単に言うと、「インターネット上のお金」のことです。
円やドルなどの法定通貨は国や銀行が管理してますが、このような中央集権的な管理をされてないのが仮想通貨です。その代わり、ブロックチェーンという特別な技術を使ってインターネット上で管理されています。

ビットコインは、仮想通貨の中で最初に誕生した「仮想通貨の元祖」です。
「仮想通貨=インターネット上のお金」、「ビットコイン=仮想通貨の王様」と理解できていれば大丈夫です。
ビットコインの概略
ビットコインの概略を表に整理しておきます。
1BTCの価格は、現在1500万円ほどですが、0.001BTCや0.003BTCなど少額でも購入できる点が特徴です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | ビットコイン(Bitcoin / BTC) |
| 誕生 | 2008年、サトシ・ナカモトにより提案 |
| 目的 | 国や銀行に依存しない「分散型デジタル通貨」 |
| 仕組み | ブロックチェーンで取引を記録・共有 |
| 発行上限 | 2,100万枚(希少性が高い) |
| 特徴 | 改ざんが困難・24時間取引・国境を超えて送金しやすい |
| 主な用途 | 投資・価値保存(デジタルゴールド) |
ビットコインのヒストリー
ここでは、ビットコインの誕生から取引開始に至るまでのヒストリーを見ていきましょう。
誕生の発端は、2008年10月に公開されたサトシ・ナカモトの論文
ビットコイン誕生のきっかけは、2008年10月にサトシ・ナカモトと名乗る人物がネット上に公開した論文でした。
その論文「Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System」には、ビットコインの基盤となる、ブロックチェーン技術を使った分散型の決済システムが記載されていました。

ちなみに、サトシ・ナカモトの詳細は明かされておらず、謎に包まれています。
リーマン・ショック当時は既存の金融システムへの疑問の声が上がっていたこともあり、この論文は大きな注目を集めました。
ビットコインの本格運用に向けて始動

論文公開後、複数の開発者が協力して、ビットコインの開発を進めました。
そして、約2ヶ月後の2009年1月3日、ビットコイン最初のブロックが作られ、その1週間後の2009年1月12日には、ビットコインの初送金が行われました。
本格運用に向けた準備の始まりです。
2010年5月22日、ビットコインによる初決済(ビットコイン・ピザ・デー)

ビットコインの初送金から約1年4ヶ月後、今度は、ビットコインを決済手段とした初の取引が行われました。
具体的には、2010年5月22日、ピザ2枚と1万BTCの交換が成立しました。当時のBTC/円レートは1BTC=約0.23円程度だったようです。
ビットコイン最初の取引が成立したこの日は、「ビットコイン・ピザ・デー」と呼ばれていて、毎年記念イベントが世界中で開催されています。
特質からみたビットコインが上がり続ける根拠
ビットコインが上がり続ける根拠について、その特質からみていきます。
具体的には、次の5つの観点から見ていきますね。
- 特定の管理がいない
- 24時間取引を可能にするP2Pネットワーク
- 希少価値を担保する、発行上限枚数
- Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)
- 4年に1度実施される半減期
特定の管理がいない
ビットコインには、法定通貨のように通貨を発行・管理する機関が存在しません。
理由は、ブロックチェーンという仕組みを利用して世界中のコンピューターがみんなで取引を分散管理しているからです。
この取引を確認する作業はマイニングと呼ばれ、多くの個人や企業が参加しています。
銀行や国といった特定の管理者に代わって、世界中のコンピューターが取引を確認しているので、「一か所のサーバーがハッキングされたら全部アウトになる」という事態は起きず、安心して取引できますね。
24時間取引を可能にするP2Pネットワーク
ビットコインは、個人間でいつでも送金や支払いが可能です。
なぜなら、銀行などのサーバーを介さずにコンピューター同士が対等な関係で直接データをやり取りする通信方式、P2Pネットワークを用いているからです。

僕自身も、ビットコインの送金が実にスムーズで、かつ手数料も安価なので助かっています。
中央集権的なサーバーに依存しない、仮想通貨を支えるP2Pネットワークが、国を跨いだ取引をさらに促進していくと思います。
希少価値を担保する、発行上限枚数
ビットコインの発行上限枚数は2,100万枚で、これが価値を維持する重要な仕組みとして機能しています。
なぜなら、発行上限があることで、ビットコインが供給過多となって希少価値が薄れるのを防止してくれるからです。
発行上限がない円やドルなどの法定通貨の価値が年々下がっているのとは対照的です。

マクドナルドのハンバーガーが、20年前には1個100円だったのが、現在は、1個190円もしますね。それだけ、円の価値が下がったということです。
というわけで、しっかりと希少価値を担保するには、2100万枚という発行上限がとても重要な意味を持っていることをお分かりいただけたかと思います。
Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)
ビットコインの取引を検証する仕組みを支えているのが、Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)とマイニングです。
Proof of Workとは、取引の承認作業を最も早く完了した者に、新規発行される仮想通貨を報酬として与える仕組みです。
また、取引承認をいち早く行なって報酬を受け取ることをマイニングといいます。
このような仕組みで、中央集権的な管理者がいなくても取引を検証することができ、取引の信頼性が保たれているのです。
4年に1度実施される半減期
マイニング報酬は、4年に1度ごとに半分になります。これを半減期と呼びます。
新規発行されるビットコインの数を抑えることで、インフレ率を減少させています。
以下が実際のデータです。
| 回数 | 年 | マイニング報酬(BTC) |
|---|---|---|
| 初期 | 2009年 | 50BTC |
| 1回目 | 2012年 | 25BTC |
| 2回目 | 2016年 | 12.5BTC |
| 3回目 | 2020年 | 6.25BTC |
| 4回目 | 2024年 | 3.125BTC |
| 5回目(予定) | 2028年 | 1.5625BTC |
半減期にはビットコインの供給が減るため、半減期とその翌年にビットコインの価格はこれまで大きく上昇してきました。

僕自身、次の半減期の大きな価格上昇を狙ってビットコインを仕込み続けています。
ビットコインに投資するメリット
ビットコインに投資することで得られるメリットを3つ紹介していきます。
- 今後の価格上昇への期待
- 国や銀行に頼らない資産防衛
- 決済手段としての活用
今後の価格上昇への期待
メリットの1つ目は、やはり今後の価格上昇を期待できることです。
繰り返しになりますが、ビットコインは、発行できる枚数が2,100万枚と限られていることが理由です。その結果、欲しい人が増えて需要が高まると、価値が上がり、価格も上がります。
実際に、これまでもビットコイン価格は、長期的な上昇傾向を示してきました。
というわけで、「デジタルゴールド」とも呼ばれるビットコインの価値と価格は今後もさらに高まっていくと思います。
国や銀行に頼らない資産防衛
メリットの2つ目は、自分の資産を自分で守れる点です。
銀行預金であれば、預金封鎖やインフレで資産が目減りする可能性があります。一方で、ビットコインには中央管理者が存在せず外部の影響を受けにくいです。

僕自身、以前は円預金や米国ETFなどで資産形成をしてましたが、現在は、余剰資金の8割以上をビットコインに投資してます。
先行きが不透明な時代だからこそ、自分の資産は自分で守っていきましょう。
決済手段としての活用
メリットの3つ目は、投資以外の用途があることです。
具体的には、一部の店舗やオンラインショッピングなどで、ビットコインを使って商品やサービスを購入できます。つまり、決済手段として利用できるということです。
また、送金にも利用でき、銀行などの第三者機関を通さないので、迅速に手数料を抑えて送金できます。

僕がビットコインをメイン証券口座からサブの証券口座へ送った際、週末にもかかわらず、10分ほどで着金を確認できました。
というわけで、今後、ビットコインによる決済や送金の活用が広がるにつれて、その価値はさらに上がっていくと思います。
ビットコインの課題
ビットコインには、今後克服していくべき課題もあります。以下、3つの課題について説明します。
- 大量の電力消費による環境負荷の軽減
- 高まる需要に対応できる取引処理速度
- マイニングを悪用した51%攻撃への対応
大量の電力消費による環境負荷の軽減

課題の1つ目は、システム維持にかかる大量の電力消費をいかに減らしていくかです。
システム維持に大量の電力が必要なのは、マイニングに使うコンピューターが高度な計算処理に莫大な電力を消費するからです。
実際に、激化するマイニング競争を勝ち抜くために、何百台ものマシンを繋ぐマイニングファクトリーも存在します。

マイニングで消費される電力量は、日本の年間電力消費量の14%にまで及んでいます。
というわけで、ビットコインのマイニングには環境への悪影響を懸念する声があり、再生可能エネルギーの利用を含めて環境負荷を軽減することが課題です。
高まる需要に対応できる取引処理速度
課題の2つ目は、高まる需要に対応できる取引処理速度を確保することです。
ビットコインブロックチェーンは1ブロックに記録可能な容量が少なく、取引処理の停滞や取引手数料の高騰が懸念されています。
具体的は、ビットコインが1秒間に処理できる取引数は約7件にとどまり、1秒間に2000件以上処理できるクレジットカードと比較しても不十分です。
今後、ビットコインの取引が世界中で増えることを考えると、一刻も早い解決が必要ですね。
マイニングを悪用した51%攻撃への対応
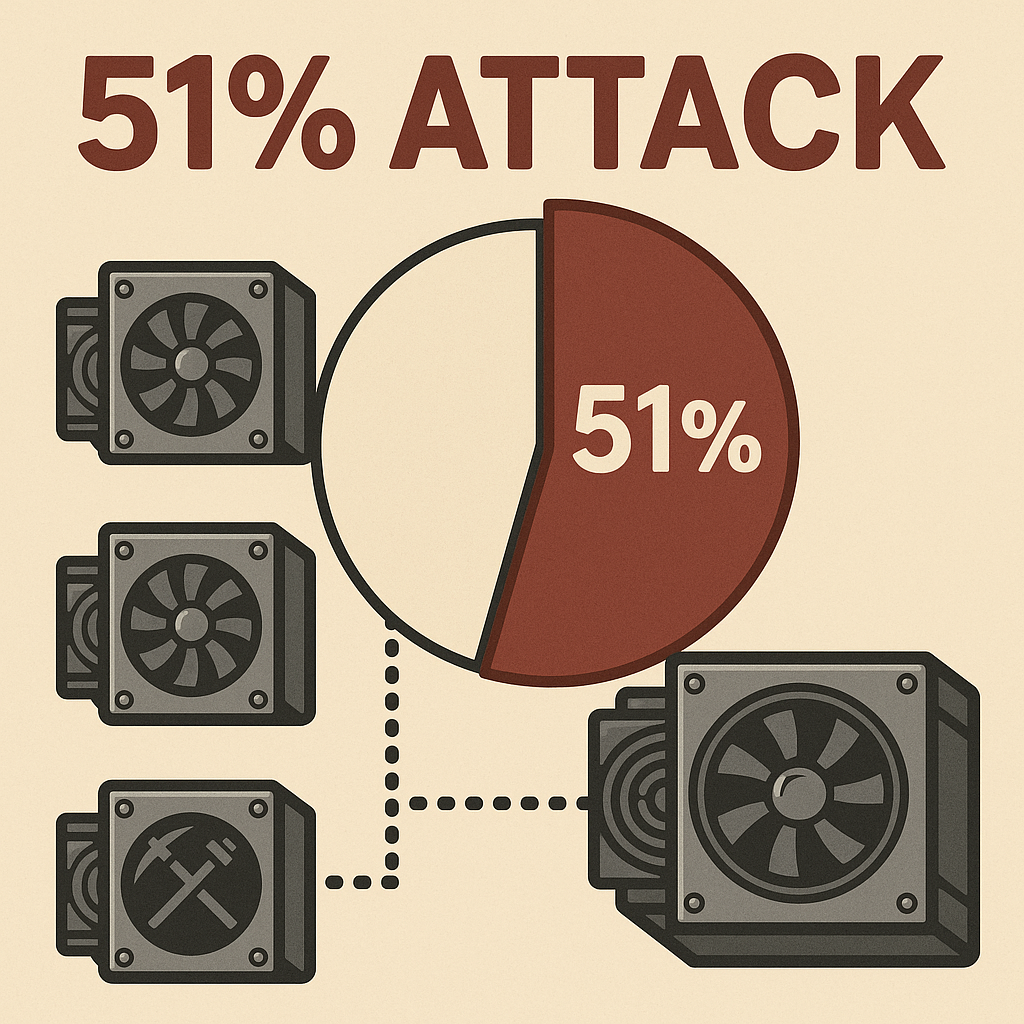
課題の3つ目は、マイニングを悪用した「51%攻撃」です。
51%攻撃とは、ブロックチェーンネットワークの計算能力の過半数(51%以上)を悪意のあるグループが支配するサイバー攻撃です。

その結果、不正な取引の承認や正当な取引の拒否、マイニングの独占などが生じます。
確かに、51%攻撃によってハッカーなどがビットコインを不正に得たとしても、ビットコインは信用を失って価格の暴落が起こる可能性があり、リスクやコストに見合う攻撃であるのかという議論もあります。
でも、このような攻撃を許してしまうと、ビットコインの安全性への信頼が崩れるので、やはりその対策が求められますね。
ビットコインはこれからどうなる?
ビットコインはこれからどうなるのか、その将来性について4つの面から考察していきましょう。
- デジタル資産として注目
- 既存の金融システムとの共存
- Web3.0を支えるビットコインのブロックチェーン技術
- 環境負荷への対応
デジタル資産として注目
ビットコインは「デジタル資産」としての立場を強固にしつつあります。
金に似た「逃避資産」として評価され、機関投資家の資金流入が進んでいることが理由です。
実際に、機関投資家向けのプラットフォームを提供するCoinbaseによると、機関投資家部門の取引量は2024年に9410億ドルと、対前年比139%増を記録しました。
というわけで、ビットコインは、法定通貨に依存しない価値保存手段として今後さらに注目されていくと思います。
既存の金融システムとの共存
ビットコインが中央銀行デジタル通貨(CBDC)と共存していく可能性もあります。
なぜなら、ビットコインの役割がCBDCと異なるからです。
具体的には、CBDCは、法定通貨のデジタル版として決済や送金の効率化を主目的としていますが、ビットコインは、分散型であり、価値保存やインフレ対策の手段としての役割が中心です。

実際に欧州中央銀行や日本銀行も、CBDCと既存の暗号資産の併存を前提とした議論を始めています。
というわけで、政府の管理するデジタル版法定通貨と、分散型のビットコインの共存という道も可能性としてありそうですね。
Web3.0を支えるビットコインのブロックチェーン技術
ビットコインはweb3.0の基盤技術としても、その重要性を増していくと思います。
なぜなら、分散型の仕組みが求めれるWeb3.0においては、その信頼性や透明性を支えるためにビットコインのブロックチェーン技術が必要になるからです。
実際に、NFTやDAOにおいて、ビットコインが取引の改ざんを不可能にする技術で貢献しています。
というわけで、ビットコインの技術的な役割は、今後も広がっていくと思います。
環境負荷への対応
デジタル資産としての存在感を高めているビットコインですが、システム維持に要する膨大な電力消費が懸念されてます。

近年、環境に配慮した投資をしたいという投資家のニーズが強くなってきています。
実際に、仮想通貨の1つである、イーサリアムは、PoSへの移行により消費電力を大幅に削減したことで、投資家の評価が一気に高まりました。
そのため、再生可能エネルギーの活用、マイニング効率の改善などの取り組みで環境への負荷を減らすことが、投資家の支持を得るためにも重要になってきています。
まとめ
この記事で解説したビットコインの歴史、特質、メリットを理解すれば、確信を持って投資できるようになるでしょう。
最後にビットコインが長期的に上がり続ける理由についておさらいしましょう。
- ビットコインの発行上限枚数は2,100万枚と決まっているので、希少価値が薄れない
- ブロックチェーンという仕組みで分散管理されているので、国や銀行に頼らない資産防衛ができる
- デジタル資産として評価され、機関投資家の資金流入が進んでいる
- 決済や送金など、投資以外の用途の拡大が期待されている
大切なことは、「正しい知識を自分の頭で理解して、自分で投資判断できるようになること」です。
この記事が、皆さんの理解のお役に立てれば嬉しいです。